なぜ私の動物が癌になったのでしょうか?
何か私に問題があったのでしょうか?
犬猫は喫煙や飲酒をしないのに、なぜ人間と同じように癌になるのでしょうか?
これらの答えは、人間の癌の発症と同様に答えるには難しいですが、遺伝的な要因(犬種、猫種、家族性等)と環境による要因(不妊手術と体重すなわち食事の管理−肥満防止、受動喫煙、汚染物質等)が、深く関与していることは間違いないと思われています。 |
|
最も重要なのは、適正体重を保つこと、肥満をさせないこと、及び早期に行う不妊手術(卵巣子宮摘出術、精巣摘出術の実施(妊娠する必要のない犬猫の場合)です。 また健康予防プログラムによる癌の予防検診により、早期発見のための診断を行うことです。これらには、7歳までは年に1回、8歳以上は年に2回の検診が必要です。
食事においては、犬猫用に作られた、栄養成分が公開されたバランスの良い食事が望ましい。また、多価不飽和脂肪酸(EPA、DHA)を含んだ食事等を与えることによって予防効果があると考えられています。 |
|
また、癌の発症が比較的低い種類の犬猫(主には雑種系が多い)や家系の犬猫を選ぶことも有効な手段です。
猫は室内で飼育する方が、猫白血病ウイルス(FeLV)に侵される機会が減るので有効です。もちろんFeLVのワクチンを接種して、FeLVが予防できれば リンパ腫の発症が減るので有効な手段となります。
現在、犬猫で汚染物質と考えられている主な物質には、殺虫剤、除草剤、アスベスト、受動喫煙、直射日光、灯油ストーブ、化学物質(塩、砂糖、水−特に汚染されたもの、火山灰、砒素や水銀等の毒物、石油、石炭、排気ガス、塗料、洗剤等)強い電磁波、放射線(放射能)等があります。 |
参考:こちらもお読みください
●犬猫の癌の予防法について
●腫瘍への対処方法
●癌が及ぼす影響について |

|
◆犬猫の癌(腫瘍)の診断と治療の手順 |
犬猫の癌の診断の7大重要点には以下の事柄を考慮して診断されます。
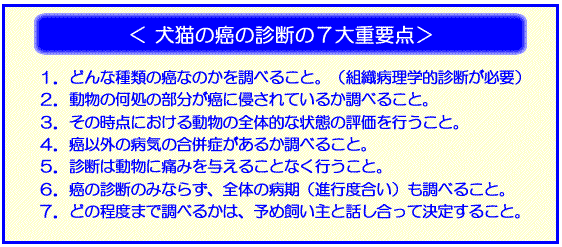
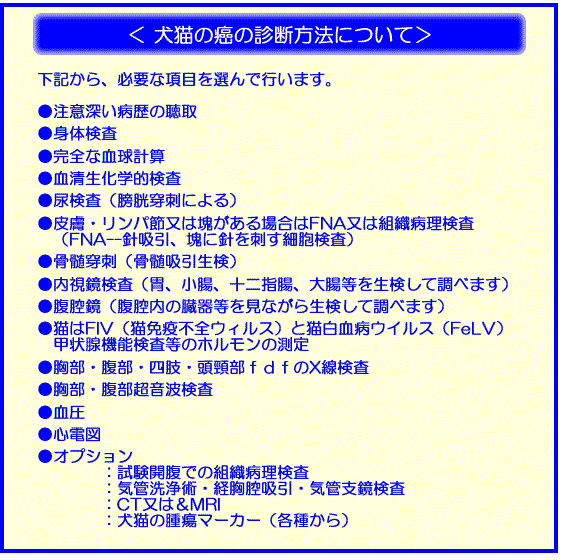
犬猫の癌の治療における7大重要点は以下の事柄を考慮して治療されます。
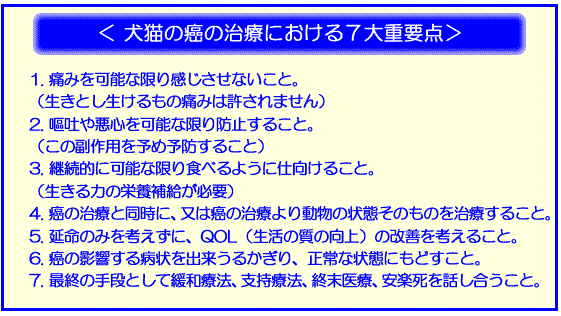
|

|
◆犬の腫瘍について |
全年齢に対しての死亡率は23%であり、10歳以上の死亡率は45%となり、これは高い確率ですが、癌は慢性疾患の一つであり、治療できない場合でも、多くがコントロールの可能な状態となります。それだけに早期発見が重要となります。犬の腫瘍の発生は人間とほぼ同じ確率と言われ、犬の腫瘍の治癒率は約30〜40%と言われています。
癌における、最大の壁は、飼い主と獣医師が、癌の治療における先入観を持つことです。抗癌剤と聞くと、副作用のある恐ろしい薬剤とすぐさま連想されることがありますが、現在ではその科学的根拠は乏しくなりつつあります。現在では癌の治療は進化して、その有効性と生存期間に大きな改善が認められています。多発する順に纏めると以下となります。
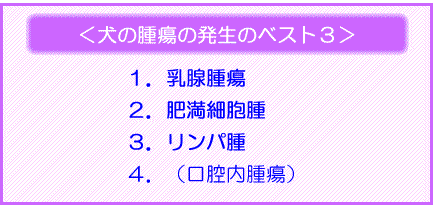
|
|
重要なことは、乳腺腫瘍は、3.5歳までに避妊手術すれば殆ど発症せず、発症しても良性の腫瘍となります。お産をする必要のない場合は、ぜひ避妊手術をお勧めします。 人間の3倍の発症率、避妊手術していない犬は7倍発症しやすい。 好発犬種は、コッカースパニエル、プードル、ボストン・テリア、フォクステリア、イングリッシュポインター、イングリッシュセッター、ジャーマン・シェパードは殆どが悪性、概して、乳腺腫瘍は50%が良性、50%が悪性です。 その悪性の50%には転移があります。

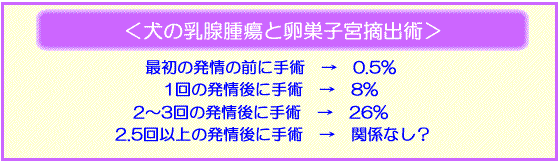
卵巣子宮摘出術はできうれば、最初の発情の前に行うのが理想的です。ゆえに5〜6ヶ月令で行えば90%以上の確率で乳腺腫瘍の発生を抑えることができます。少なくても1歳までに行えば80%以上抑えられるでしょう。またよく論議される問題ですが、乳腺腫瘍摘出術の際に、卵巣子宮摘出術を行うべきかどうかですが、犬の場合は基本的なルールとしては事情が許せば、行う方が良いとされています、特に発情期にて腫瘍の増殖傾向が認められたら行うべきものとされています。これらの理由は犬の乳腺腫瘍の細胞内には、50%以上の確率で、エストロジェン・プロジェステロン受容体が存在しているからです。
問題は如何に乳腺腫瘍摘出術と卵巣子宮摘出術を同時に行うかです。乳腺腫瘍が小さい場合には、卵巣子宮摘出術を先に行い、その後、乳腺腫瘍摘出術を行えばよいのですが、問題は乳腺腫瘍が大きくて多数ある場合です。
そんな場合は先に乳腺腫瘍摘出術を行い、麻酔が安定していれば、その後に卵巣子宮摘出術を行います。しかしこの際のルールとしては、乳腺腫瘍摘出後は、すべての手術器具、手袋、滅菌布等を新しく交換しなければいけません。この理由は、腫瘍細胞を腹腔内に撒き散らす機会を減ずるためです。
悪性の所見を疑うには、大きな腫瘍(5cm以上)、多発性、潰瘍化、再発性可動性がない、リンパ節に転移、急速に発育、短頭種、妊娠時、純粋種(特に大型犬)、良性を疑う所見は、腫瘍が硬くて骨とか軟骨のように感じるものは良性が多い。
犬の乳腺腫瘍はどこに転移するのか?
転移は肺(疼痛、咳、呼吸困難等)が一番多いですが、どこにでも転移すると考えます。例えば脳神経系(痙攣・発作)骨、関節系(跛行、麻痺)、消化器系(嘔吐、)、泌尿器系(血尿)の各症状が現れやすく、その他胃、皮膚、脾臓、腎臓、肝臓等に認められます。
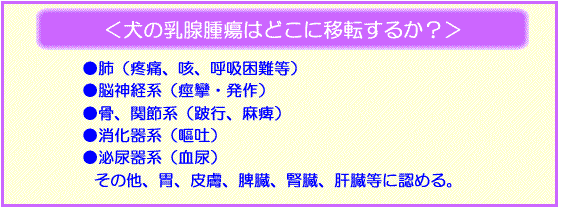
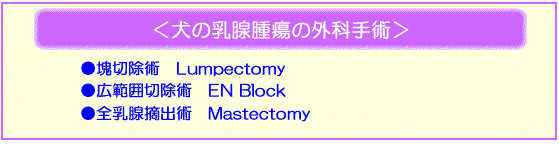
犬の腫瘍ベスト3へ戻る |
|
好発犬種は、ボクサー、ボストン・テリア、イングリッシュ・ブルドッグ、ブルテリア等です。平均年齢は8.5歳、性差はありません。
注意すべきは、胃や十二指腸に潰瘍を持つ確率が35%〜83%との報告がある点です。この腫瘍は、一見、膿瘍や脂肪腫瘍に間違いやすいので、どんな塊に対しても針吸引をすべきです。
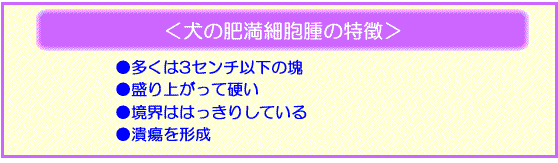
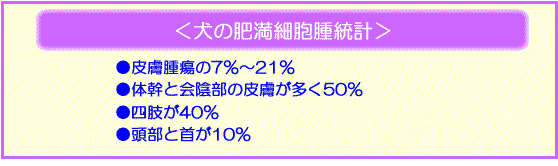
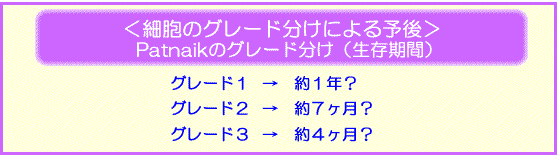
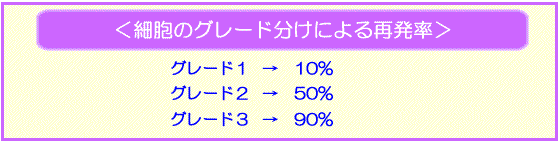
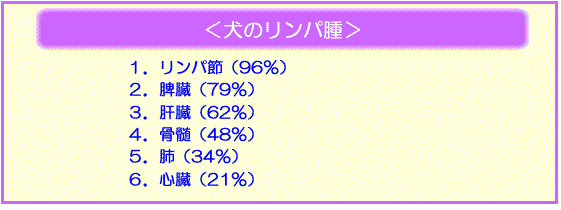
予後はグレード、腫瘍の発生から7ヶ月以内に手術したもの、5cm以内の大きさ、成長速度が遅いもの、リンパ節に転移がないもの、再発性でないもの、好発犬種でないもの、消化器症状がないもの、皮膚粘膜接合部に発症していないもの等である。
犬の腫瘍ベスト3へ戻る |
|
好発犬種はボクサー(他の犬種より10倍の発症率)、 セント・バーナード、ブルドッグ、バセット・ハウンド、エアデールテリア、プードル、ゴールデン・レトリーバー、ブルマスチーフ等で、多くは、中年齢での発症が多いですが、まれに若年性での発症も認められます。犬のリンパ腫の発症要因として、除草剤や磁場の影響が疑われています。
最も多い臨床症状は、全身の末梢のリンパ節の腫大で、これは身体検査でも見つけやすい全身性のリンパ節症のタイプです。肝臓の腫大、脾臓の腫大、骨髄の転移(10%)が約80%に認められます。
多くの症例で、全身の末梢のリンパ節の腫大があるにも関わらずに、比較的元気な場合が多いようです。この場合の診断は、外科手術にて切除(膝窩リンパ節が行い易い)したリンパ節の組織学的検査(悪性リンパ球の浸潤)によります。
普段リンパ球系の細胞が存在しない、臓器であれば、細胞診にても診断できる場合があります。 また消化器型の症状もあり、IBD(炎症性腸疾患)との鑑別も重要です。 最近、若いダックスフンドに消化器型のリンパ腫が認められることがあります。 縦隔洞型は、呼吸困難、呼吸速拍が認められる場合があります。
皮膚型のリンパ腫もあり、多数の皮膚結石が短時間に進行することがあります。 これは菌状息肉腫と言われ、長期間に少しずつ進行します。また非リンパ節型もあり、眼、中枢神経系、心臓、腎臓、膀胱、鼻腔等これらは、侵された部位によって、さまざまな症状が現れます。
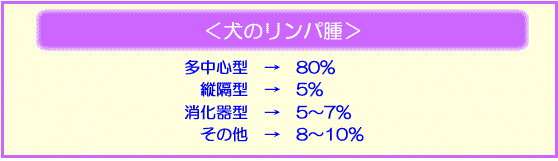
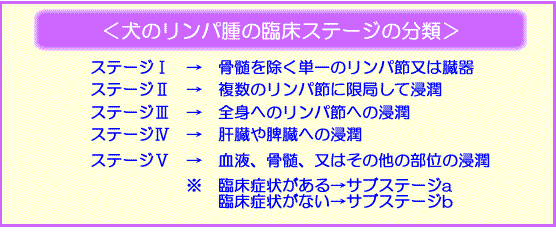
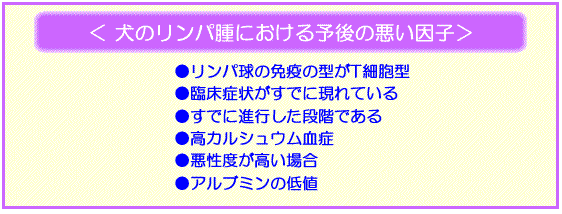
犬のリンパ腫は化学療法に最も反応する造血系の悪性腫瘍です。治療前に腫大したリンパ節の大きさを測定しておくと、その反応の程度が判ります。縦隔型で高カルシュウム血症が存在する場合は、胸部X線検査で評価しますが、その予後はなかなか難しい。
リンパ腫の治療において最も注意すべきは、治療前のステロイドの投与です。 リンパ腫の治療で多剤併用化学療法を予定している場合等は、その前に使用すべきではありません。薬剤の耐性の理由で、治療の反応が悪くなることが知られています。但し本格的に抗癌剤療法を始めないで、単に延命療法を飼い主が選んだ場合は、使用しないより格段に有効となる場合が多いようです。
犬の腫瘍ベスト3へ戻る |

|
◆猫の腫瘍について |
猫の腫瘍は犬の腫瘍の発生の約半分の発症率と言われています。猫では総じて約70%の腫瘍が悪性で、造血系、皮膚、軟部組織の腫瘍が多いと言われます。白い猫の扁平上皮癌は、白くない猫に比べて5〜13倍発症しやすいと言われています。多発する順に纏めると以下となります。
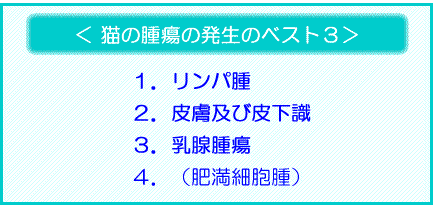
|
|
約500頭に1頭の発症率で、猫の造血系の腫瘍では、リンパ腫、肥満細胞腫で、犬は逆となります。縦隔型はFeLV(+)が77%と多く(多くが胸水、平均発症年齢2.5歳、胸腺のTリンパ球から発症します。リンパ腫でない胸腺腫は高齢、FeLV(−)が多い)、消化器型はFeLV(−)が77%と多く(50%が小腸で、胃から結腸まで侵される、平均発症年齢8.9歳、D細胞性起源から多く発症する)
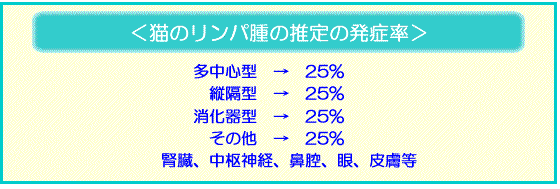
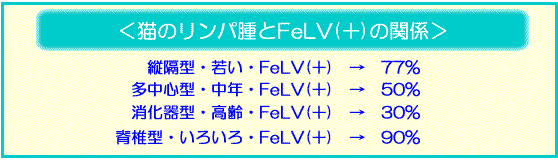
猫のリンパ腫は、犬と違い内臓が侵される割合が高く、腹部の検査(触診からX線検査から超音波検査)が特に重要となります。またステージ分けも難しい場合があり、できうれば骨髄吸引を行う。 また同時に猫白血病ウイルス(FeLV)とFIV(猫免疫不全ウィルス)の検査をすべきです。
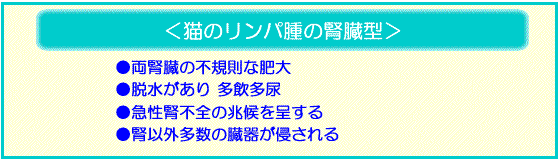
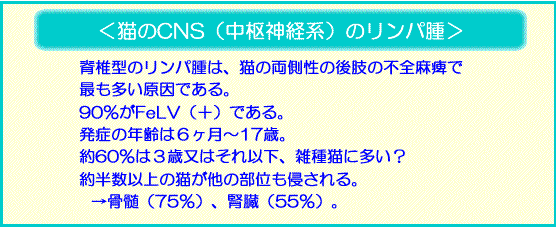
猫は室内で飼育する方が、猫白血病ウイルス(FeLV)に侵される機会が減るので有効です。もちろんFeLVのワクチンを接種して、FeLVが予防できれば リンパ腫の発症が減るので有効な手段となります。
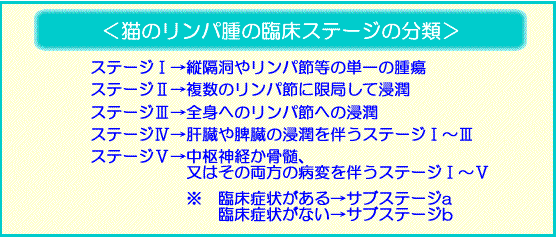
大部分(90%)のリンパ腫は高〜中グレードである。しかし、高分化型(低グレード)のリンパ腫は主に消化器で診断されることが多く、このタイプはリンパ球性プラズマ細胞性胃腸炎や炎症性腸疾患などから腫瘍へ進行する可能性があることを示唆しています。概して、高分化型(低グレード)のリンパ腫は、化学療法に良く反応するため、長期の生存が見込まれます。
猫の腫瘍ベスト3へ戻る |
|
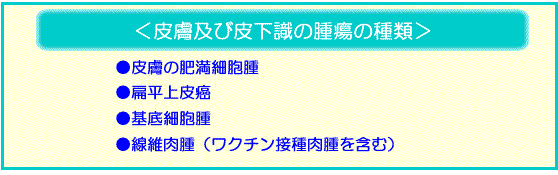
“猫の皮膚(体表)の腫瘍の約70%は悪性、犬の皮膚(体表)の腫瘍の約70%は良性”とわかりやすく表現されますが、概して腫瘍の悪性度は犬の40%に対して、猫の悪性度は70%、犬より猫の方が悪性度が高いものです。
猫の皮膚の腫瘍では肥満細胞腫が最も多く、ほとんどが頭頸部に発症します。孤立性が多いですが多発性もあります。好酸球性肉芽腫との鑑別を要します。20%近くが脾臓にも転移します。
扁平上皮癌は、太陽の光によって誘発されることが知られています。特に高齢猫、毛の少ない、皮膚の色素が少ない猫で外に出る機会が多い猫に起こります。始めは引っかき傷のように見えますが、頭部の潰瘍病変が特徴です。
白い猫の扁平上皮癌の発生する確率は、約5〜13倍と種々報告されています。病変は鼻の平面、耳介部、眼瞼が多いがまれに肢にも発生します。扁平上皮癌の治療は、広く辺縁を含めた外科手術が一般的です。
基底細胞腫は、頭頸部と体幹によく認められます。良性は色素沈着があり、孤立性の膿胞や硬い塊として認められることが多い。悪性は、色素沈着がなく、浸潤性があり、頭頸部の発症が多い。外科手術が適応となります。
主に猫白血病ウイルス(FeLV)ワクチン由来の、ワクチンの接種部位に起こる線維肉腫は、米国のように猫に狂犬病の予防接種をする(複数のワクチンを接種する程起こり易くなる)機会の少ない我国では、まれな発症となっています。接種後は、飼い主によるその部位の観察が必要となります。
猫の腫瘍ベスト3へ戻る |
|
猫10万頭中→約13頭、雌猫は10万頭中→約26頭に発症します。
シャム猫は平均9歳から発症するので早期からの検診が必要です。
その他の猫の平均発症年齢は10〜12歳。起こる場所は、犬は前からである第一乳腺から発症することが多いが、猫は後ろの乳腺から発症することが多い。
猫の乳腺腫瘍は時に、炎症性癌腫と肥満細胞腫の鑑別が必要な場合があります。その場合はFNA(針吸引ー腫瘍に針を刺して細胞を調べる)が必要となります。
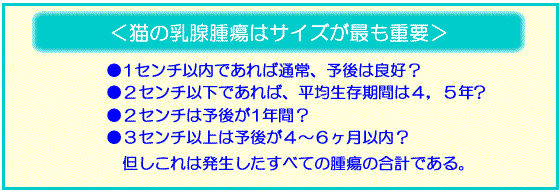
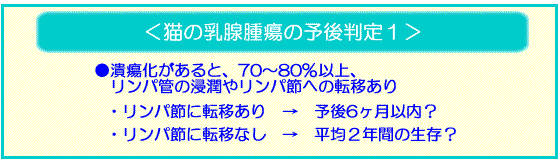
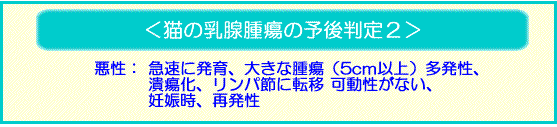
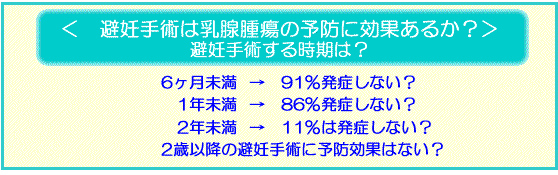
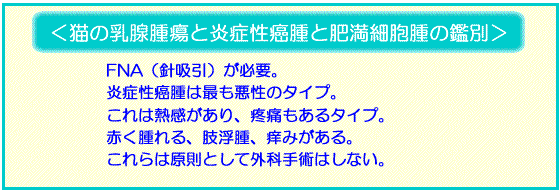
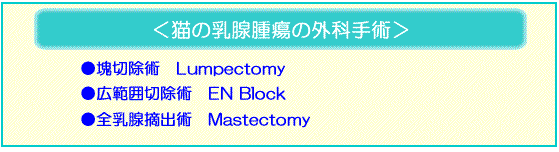
猫の腫瘍ベスト3へ戻る |